
口・のどの疾患

口・のどの疾患
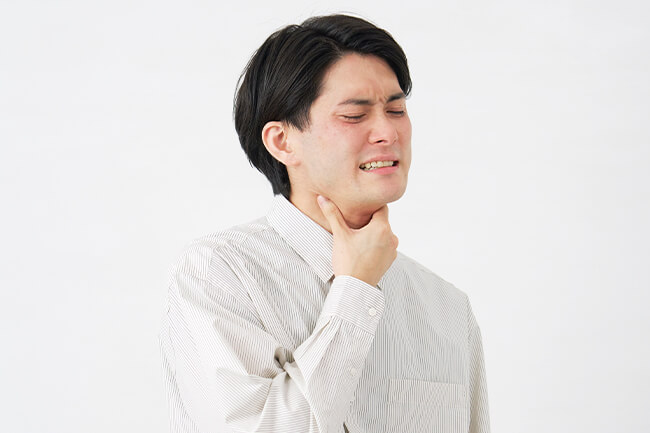
扁桃腺に細菌やウイルスが感染して炎症を強く起こす病気です。のどの痛みや発熱などの症状がでます。内服とうがいで治療しますが、悪化してしまうと扁桃周囲炎や扁桃周囲膿瘍などの疾患に発展してしまう場合もあるため注意が必要です。
急性扁桃炎が悪化してしまい、扁桃腺の周りに膿がたまる病気です。のどの痛みが強く、口が開かない、食事がとれなくなることもあります。たまった膿に注射針をさして抜いたり、切開して膿を出したりする必要があり、多くは入院が必要となります。
いわゆるのど風邪です。喉の痛みや熱などが出ます。内服や上咽頭処置、ネブライザー治療などが効果的です。
舌の付け根にあるヒダ(喉頭蓋)に炎症が強く起きる病気です。のどの激しい痛みや熱、飲み込みづらい症状がでます。喉頭蓋の腫れが強くなると喉を塞いでしまい、窒息する危険性もある病気です。点滴や内服、ネブライザー治療を行うために入院が必要となることが多いです。
風邪に続いて声帯に炎症が及んだり、カラオケなどで大きな声を出しすぎたりすると、声を出すヒダが腫れて声がかすれたり、でなくなったりします。内服治療やネブライザー治療が有効ですが、治療の原則は声の安静です。
大声を常日頃出す職業の方や、お子さんにできやすい、いわゆる声のヒダの「ペンだこ」です。声の安静が治療の基本です。ポリープ様声帯はお酒やタバコをよく飲む方に見られます。ガラガラ声となることが多く、治療には手術が必要となることが多いですが、禁酒や禁煙ができないと再発しやすい病気です。
のど周辺に何らかの違和感や不快感がある状態です。喉がイガイガ(ザラザラ)する、喉に何かがつかえている感じがする、なんとなく痛いなどの症状があります。原因はアレルギーや逆流性食道炎、ノドの乾燥、ストレスなどが考えられていますが、適切な治療をしても症状が長引く方が多いです。
逆流性食道炎の症状の一つとして、声がれやノドの違和感をきたした状態です。逆流性食道炎のための内服治療や生活習慣の改善(食事を摂ってからすぐ横にならない、減量など)をすることで改善することが多いです。
ヒトは食べ物を飲み込むときに、ノドの色々な筋肉が互いに上手く働きなながら食べ物を食道に送りこみます。(嚥下)ノドの周辺の筋肉の働きが悪くなってしまうとスムーズに嚥下できなくなってしまい、気管に食べ物や飲み物が入ってむせこんでしまいます。(誤嚥)ノドの筋肉の働きは加齢や病気により体重が減ったり、脳梗塞などの神経の病気にかかると衰えてしまうので、嚥下障害が起こった場合は衰えた筋肉をもう一度鍛え直したり、飲み込み方を工夫したり、食べ物にとろみをつけたりして誤嚥を予防します。皆様が「最近、食事のときにむせこむことが多くなった」と感じたら、ぜひご相談ください。
内視鏡による嚥下の検査やノドの筋肉の鍛え方などアドバイスさせていただきます。
口の中の粘膜に炎症が起きた状態です。粘膜が赤くなったり、びらん・潰瘍ができます。原因は免疫の低下、ストレス、睡眠不足、ウイルス感染、真菌感染、歯の機械的刺激など様々です。軟膏や内服で治療しますが、2週間経っても治りが悪い場合はがんなどの可能性も考えて対応を考えなくてはいけません。
味が感じにくくなったり、本来の味と別の味を感じてしまう状態です。今のところ原因は特定されていませんが、栄養不足やストレス、貧血など、複数の要因が重なり合って影響している場合があります。主に亜鉛などの内服で治療を行います。
扁桃炎の影響や顎関節症の影響で口が開きにくくなる状態です。原因となる病気の治療によって改善することがほとんどです。
寝ているときにいびきがひどく、ときに呼吸が止まってしまう病気です。主な原因は肥満や顎が小さいこと、扁桃腺が大きいこと、鼻呼吸が上手くできていないことなどがあります。睡眠時無呼吸症候群は夜間の良質な睡眠が得られないことに起因する日中の眠気や集中力の低下にとどまらず、抑うつや高血圧、糖尿病、不整脈などの心疾患にも影響してきます。日中の眠気の症状が強かったり、ご家族から寝ているときに呼吸が止まっているなどの指摘があった場合は当院へご相談ください。検査や治療ができる病院へのご紹介させていただきます。
TOP